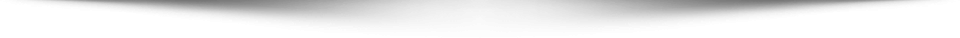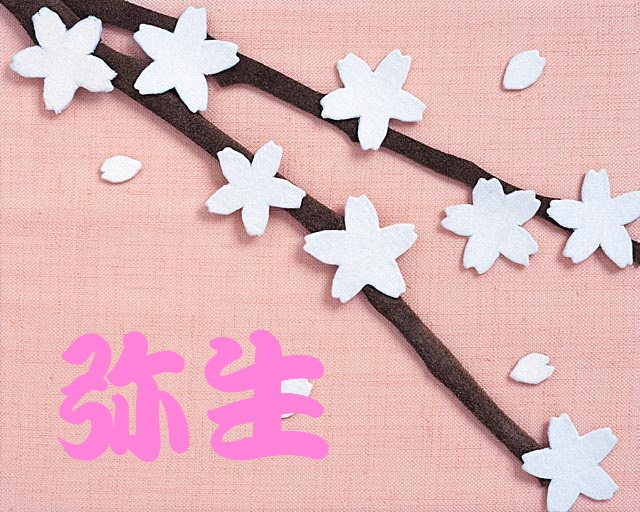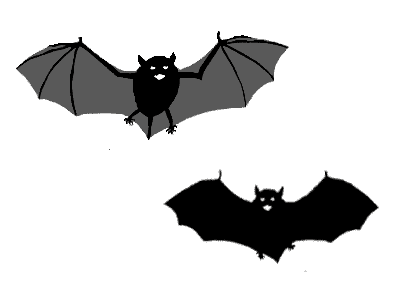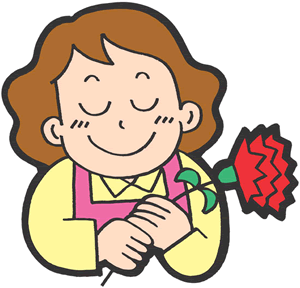
きょうは母の日
母の日というと、5月の第2日曜日とだれでも知っていますが、これはアンナ・ジャービスという女性が母の命日に、亡き母をしのぶ記念の会を催し白いカーネーションの花束を霊前にたむけ、参会者に分けたのが始まりといわれています。でもこれはアメリカでの話で、日本の母の日は、5月5日ということを、御存じですか?『国民の祝日に関する法律』には、こどもの日(5月5日)は、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」と書かれています。そして「幸福なるこどもは幸福なる母の所産である。母の慈愛に感謝し、母の努力に報い、母を祝福する意義がここにある」と説明されています。
でも、母への感謝は、法律にしばられたくないというのでしょうか、現在ではアメリカ流になっています。
母親を、敬いましょう。
「両親を尊敬しなさい。そうすれば、主であるわたしが与える国で、しあわせな一生を送ることができる。」 (出エジプト20:12)
母親には、従いましょう。
「かたくなで、逆らう子がおり、父の言うことも、母の言うことも聞かず、父母に懲らしめられても、父母に従わないときは・・・ 町の人はみな、彼を石で打ちなさい。」
(申命記21:18 21)
母親の生活が守れれるように、心を使いましょう。
「(十字架の上の)イエスは・・・ その弟子に『そこにあなたの母がいます。』と言われた。その時から、この弟子は彼女を自分の家に引き取った。』(ヨハネ19:26,27)...